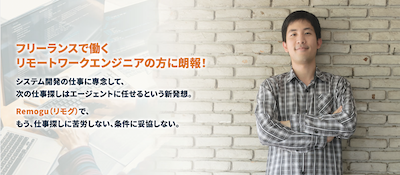精鋭の若手エンジニアが現場に寄り添い生み出す、新時代の生成AIソリューションー株式会社Kiei 島田将太郎さん

生成AIを軸に、企業の課題解決プロジェクトを幅広く展開するスタートアップ企業・株式会社Kiei。社員はなんと、現在全員20代。高い熱量をもって成果を追い求めながら、自由な働き方を実現しているそうです。
今回はそんな同社の開発責任者である島田将太郎さんに、生成AI技術に対する思いや今後の組織づくりの方針、AI時代を迎えた今、理想とされるエンジニア像などについて伺いました。
企業と生成AIをつなぐ「ラストワンマイル」を担う
―島田さんがAIを活用した事業に興味を持った理由について教えてください。
もともと大学ではAIを専攻していましたし、遠くない未来、間違いなくAIが社会の中心になっていくと確信していたのが大きいです。
AIは、一大ムーブメントとしてさらに拡大していく市場でもあります。そこに対して感度を高く持ち、プロジェクトの成功経験を積み上げることには、社会的に大きな価値があると考えました。企業はもちろん個々人の生活をより良いものにする――そんな使命に対して、最も寄与できるソリューションがAIなのだと捉えています。

株式会社Kiei 開発責任者 島田 将太郎 氏
麻布高校在学中に初めてプログラミングに興味を持ち、慶應大学理工学部在学中から複数の機械学習の開発プロジェクトに従事しつつ、テック系スタートアップにてプロダクト開発をリード。その後、AIの社会実装というテーマに共感しKieiに参画し、生成AIを活用した開発プロジェクトを複数牽引。
―Kieiは「AIの社会実装によって、日本の競争力を高めること」をビジョンに掲げていますよね。そこにはどんな思いがあるのでしょうか?
生成AIの登場によって、企業のTo-be像は急激な進化を遂げています。一方、実際の企業はどうしても線形的な、積み上げ型の成長しかできていません。As-isとTo-beの差分がどんどん広がってしまうのは、生成AIに対して知識が不足しており、社会実装する方法がわからないためです。当社はそこを「AIのラストワンマイル」であると捉えました。我々のようなAI集団が外部から企業を支援させていただき、差分を埋めることで、多くの企業、ひいては日本そのものの発展につなげたいと考えています。
生成AIの知見を駆使し、あらゆる業界に永続的価値を提供
―Kieiは、生成AIを用いて具体的にどのようなサービス提供をしているのでしょうか?
コンサルティングと、それに伴うシステム開発です。まずは生成AIの知見を生かしたコンサルティングを行った上で、生成AI技術を組み込んだシステムを開発し、業務に適用させます。
横断的なサービスなので、対応可能な業界は問いません。社会的にインパクトがある案件で言うと、大手企業様とご一緒するケースも多いですね。全業界に共通するのは、企業のヒト・モノにかかわる仕組みやプロセス、業務フロー、データの流れに対して生成AIを活用する点です。各クライアントが持っているアセットと生成AIを組み合わせることによって、事業を再定義したり、新たな永続的価値を提供しています。
決して理想論で終わらない、「現場主義」の課題解決が強み

―生成AIを用いたコンサル企業は今後も増えていくと思いますが、Kieiは競合他社に対してどのような強みを持っているのでしょうか?
明確な強みの一つは、「現場主義」です。例えば大手コンサルティングファームの場合は、企業の上流から参入し、プロジェクトや施策を打ち立てて現場に落としていくケースがほとんどです。ですがそれでは、現場への適用が十分に浸透しない可能性があります。理想論で終わってしまうんですね。
そういった状態に陥らないよう、我々はまず現場に入り、実際に現場で起きている課題の解決に臨みます。現場の課題が最終的に、経営など上流の課題につながることも多いですよ。現場主義でクライアントに寄り添い、本質的な課題解決をするのが、当社のスタンスであり強みです。
―生成AIのモデル選定やシステム開発で大事にしていることはありますか?
もちろん生成AIのモデルごとに得意不得意な分野がありますから、適したモデル選定は行います。ただ、大事なのはモデル選定そのものよりも、現場の課題にフィットしたLLMの使い方をすることです。適切な評価軸を設定し、課題解決に向けた活用ができるかどうか。開発においては、この検証部分を重視しています。
―なるほど。技術面では何がキーワードになるのでしょう?
RAGとAIエージェントでしょうか。「LLMが持ち得ないクライアント企業独自のデータを、LLMとどう組み合わせて作っていくか」。ここをソリューションとして提案するにあたり、RAGは大きなキーワードになります。
AIエージェントも同様です。当社では業務フローのプロセスを自律的に判断・実行してくれる生成AIを「AIエージェント」と定義しています。これまで人が行っていたプロセスをいかにしてAIに代替するかーーここが、もう一つの具体的なソリューションであり、外せない技術です。
若きエンジニアが熱量を持って自由に働き、成果を追い求める

―Kieiの開発チームについても教えてください!
エンジニアは全体で40名ほどで、そのほとんどが20代かつ、生成AIの技術者です。メンバーは業務委託やインターンなど立場がさまざまですが、働き方は本当に自由です。
会社全体の方針として、時間労働で縛るよりもアウトプット、成果物を重視しているので、フルリモートの方もいますし、リモートワークと出社のハイブリッド型など、ご自身が一番成果が出せる方法で働いてもらっています。
―若手が集まるチームなんですね。どんなメンバーが多いのでしょう?
技術にワクワクできる、熱量の高いメンバーが多いですね。知的好奇心も旺盛で、自走力の高い人が集まっています。
若さゆえの熱さと言ってしまえばそれまでですが、ちょっと冷めた目線を持った方がうちの会社に入っても、あまり面白くないかもしれません(笑)。
―生成AIエンジニアの育成という観点で、何か取り組みはされていますか?
研修資料は用意していますし、メンバー同士の情報共有やチーム単位での勉強会も実施しています。
ただ、生成AIを学ぶために一番効果的なのは、何よりエンジニア自身が生成AIをフル活用することです。社内外の生成AIを自由に使ってもらい、業務効率化や成果物の品質向上に活かす。こういう仕事のスタンスの重要性を、日々メンバーに伝えています。
頂点を目指して――新しいエンジニア組織の在り方を模索

―数年先の組織の未来について、目標や戦略があればお聞かせください。
我々が「フォワードデベロップメントエンジニア」と呼んでいる人材が活躍できる組織を作っていきたいです。例えば営業ができる、現場でクライアントと会話しながらデモ開発ができる、展示会で自社をPRできるなど――簡単に言えば、「会社の外の現場に出ていける新しいエンジニア」ですね。
エンジニアリングマネージャーやテックリードのように、技術の専門性を深堀りする人材の役割は、今後どんどんAIが担っていくことになるでしょう。では、エンジニアに求められる別の付加価値とは何かを考えたときにたどり着いたのが、フォワードデベロップメントエンジニアだったんです。ここにPM的人材を加えた二軸で、今後の組織づくりをしていきたいと思っています。
この展望の根本にあるのは、やはり時代性ですね。明確なものが何もわからない時代の中で、事業の形はどんどん変わっていくでしょう。それでも常に「クライアントに価値提供ができる組織」をあるべき姿として持ち、頂点を目指して進化し続けたいという思いがあります。
―では今、生成AIを目指すエンジニアに向けたアドバイスもお願いします!
ここ数年でAIは爆発的に広まり、民主化を遂げました。「作る側」の視点でどうAIの精度を出すかだけでなく、今後は「使う側」としてAIをどう活用するのかが、より重視されるでしょう。
その中で生成AIエンジニアに限らず全技術者に普遍的に求められるのは、何より知的好奇心を持って、主体的に技術をキャッチアップする能力です。今後の社会は、どこに行って何をするにしても、生成AIが登場するはずです。どうせいつか触れるなら、今情報をキャッチアップして使ってみればいい。少しでも早く技術に触れ、肌で理解することを大切にしてみてほしいです。
Remoguは「ヒト」が利用価値を高めてくれた
―貴重なお話をありがとうございました。最後に、Remogu(リモグ)を利用してフリーランスエンジニアの方を採用された感想についてもお伺いできますか?
今はRemoguさんからは、10名ほどのAIエンジニアに参画してもらっています。個人的に利用価値を高めてくれたのは何より担当者の方ですね。人柄や細かな気遣いなどに対して、非常に満足を感じています。