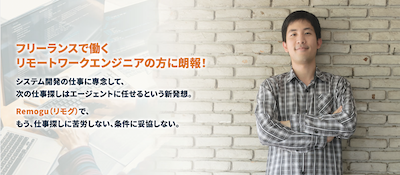リモートワークのデメリットとは?リモートワークを導入した企業と従業員が直面する課題とその対策

ここ数年で急速に広まったリモートワーク。柔軟な働き方を実現できる手段として、多くの企業や働き手から支持を集めています。オフィスに出社せずに、自宅や好きな場所で働けるというメリットは大きく、今では新たな働き方の選択肢として定着しつつあります。
しかし、リモートワークには「自由さ」と引き換えに、見落とされがちな“デメリット”も存在します。例えば、コミュニケーションの難しさや働きすぎによるメンタルヘルスの悪化など、実際に働いてみて初めて気づく課題も少なくありません。
この記事では、企業側と働く側の両面からリモートワークのデメリットを整理し、よくある課題とその対策について具体的に解説していきます。リモートワークを前向きに導入・継続していくために、見逃せない“課題と向き合う視点”をお届けします。
1. 企業側のデメリットと対策
リモートワークを導入する企業にとって、最も大きなハードルは「従来の働き方とは違うマネジメント」が求められる点です。単に場所を変えるだけではなく、社内の体制や制度そのものの見直しが必要になるため、さまざまな課題が浮き彫りになります。
1-1. コミュニケーション不足
対面での何気ない会話や会議後の雑談が減ることで、情報共有の質やスピードが低下してしまうケースがあります。特に部門をまたいだ連携や、チーム内での信頼関係構築には影響が出やすくなります。
対策としてツールを活用して、意識的に“雑談の機会”を設けるのが有効です。SlackやZoomを使ったバーチャル朝会や、定例のオンライン1on1を通じて、信頼関係を築く仕組みを整えることが重要です。
1-2. 労務管理の難しさ
オフィス勤務であれば「出社=勤務開始」と明確ですが、リモートではその境界が曖昧になりがちです。その結果、長時間労働の温床となったり、成果の把握が難しくなったりすることも。
勤怠管理ツールの導入や、成果ベースでの評価制度を導入することで、“働いているかどうか”よりも“どんな成果を出しているか”に目を向けたマネジメントが可能になります。
1-3. 情報セキュリティのリスク
自宅やカフェなど、オフィス以外の場所で業務を行うことで、情報漏洩のリスクが高まります。特に個人PCの使用やフリーWi-Fiの利用など、セキュリティ面での意識差が課題になりがちです。
VPNやセキュアなクラウドストレージの利用、社内ルールの明確化と教育が不可欠です。あわせて、IT資産管理ツールで端末の状態を常時把握できるようにしておくと安心です。
1-4. 人事評価の難しさ
プロセスが見えづらいリモートワークでは、「頑張っている人」が埋もれてしまうリスクがあります。対面での接点が少ないため、マネージャーが適切に評価できていないケースも珍しくありません。
OKRやMBOといった目標管理制度を導入し、成果とプロセスの両面で評価する体制を整えることがポイントです。また、定期的な振り返りやフィードバックの場を設けることも評価の精度向上につながります。
1-5. 教育の難しさ
未経験者や若手のメンバー教育の難しさもリモートワークのデメリットといえます。オフィスに出社していれば、隣ですぐ質問やフォローをすることもできますが、リモートワークは基本的にはオンラインコミュニケーションが主軸となります。メッセージやオンラインミーティングで教育を行い、会社の文化を伝え、担当業務の円滑な遂行をしてもらわなくてはいけません。
そのためオンボーディングをどうするのか、誰が教育係になるのかなど、事前に受け入れ体制を整えていく必要があります。

2. 働く側のデメリットと対策
リモートワークは「自由で快適な働き方」と捉えられがちですが、実際に働いてみると、思わぬストレスや不安を感じる場面も少なくありません。ここでは、働く側が抱えやすいリモートワークの課題と、その乗り越え方を紹介します。
2-1. 孤独感やメンタルヘルスの問題
一人で過ごす時間が長くなることで、孤独感や孤立感を感じやすくなります。相談相手がいない環境では、仕事の悩みやプレッシャーを抱え込んでしまい、メンタル不調につながるリスクも。
チーム内でのこまめな声かけや、バーチャル雑談の機会を設けることで心理的な距離を縮めましょう。また、企業側がメンタルヘルス支援の窓口を用意しておくことも、安心して働ける環境づくりに効果的です。
2-2. ワークライフバランスの崩壊
通勤がない分、時間にゆとりが生まれる一方で、「つい働きすぎてしまう」「オンとオフの切り替えが難しい」といった声もよく聞かれます。仕事の終わりが見えにくく、気づけば長時間労働になっているケースもあります。
始業・終業時間を自分でしっかり決め、カレンダーやアラームを活用してスケジュール管理を徹底しましょう。作業スペースと生活スペースを物理的に分けるのも、オンオフの切り替えに有効です。
2-3. キャリア形成の機会減少
オフィスでの雑談や偶然の会話から得られる「学び」や「チャンス」が、リモート環境では得づらくなることがあります。また、先輩社員からの指導やOJTなども不足しがちで、成長実感が薄れてしまうことも。
社内外問わず、意識的に学習の機会を設けることが大切です。オンライン勉強会や資格取得支援制度、メンター制度の活用など、継続的にスキルアップできる仕組みを取り入れていきましょう。

3. リモートワークのデメリットを克服するためのポイント
リモートワークの導入・定着にあたっては、単なる「場所の自由」だけでなく、“働きやすさ”や“生産性の継続性”をどう実現するかが問われます。
リモートワークならではの課題を放置してしまうと、働き手のモチベーション低下や企業の業績への悪影響につながる可能性もあります。だからこそ、企業と働く側の双方が「課題と向き合う姿勢」を持ち、継続的に環境をアップデートしていくことが重要です。
そのためには、ツールや制度を導入するだけでなく、それをどう活用し、現場にどう根づかせるかがカギとなります。ここでは、リモートワークのデメリットを克服し、よりよい働き方を築くための具体的なポイントを3つに分けてご紹介します。
3-1. テクノロジーを味方につける
リモート環境では、適切なツールの導入と使いこなしが生産性やチームの連携力を大きく左右します。たとえば、SlackやZoomといったコミュニケーションツールは、リアルタイムでのやり取りや会議を可能にするだけでなく、ちょっとした雑談や相談の場としても機能します。NotionやBacklogなどの業務管理ツールは、進捗の可視化やタスクの割り振りに効果的です。
また、勤怠管理や人事評価に関しても、勤怠ツールやOKR管理システムの活用によって、遠隔でも透明性と公平性を保つことが可能になります。導入時には、使用方法のレクチャーやマニュアルの整備を行い、誰もがスムーズにツールを使える環境を整備することが大切です。
さらに定期的に利用状況を見直し、現場に合ったツールの選定や改善を行うことで運用の質も高まります。
3-2. 仕組みや制度を整える
働き方が変われば、それに合わせた仕組みや制度のアップデートが欠かせません。たとえば、始業・終業時間のルール、残業の可視化、休暇取得の流れなど、基本的な勤務ルールを明文化しておくことが重要です。これにより、働く側は不安なく業務に集中でき、管理側もフェアな対応がしやすくなります。
また、成果に応じた評価制度の設計もポイントです。リモートワークでは「働いている様子」が見えにくくなるため、プロセス評価と成果評価のバランスを取りながら、納得感のある仕組みを整えましょう。さらに、リモートワーカーの孤立を防ぐためのオンボーディング施策や、メンタルケアの仕組み(例:EAP制度の導入やメンタルチェックの実施)も有効です。
制度は作って終わりではなく、“運用できて初めて機能する”もの。定期的なフィードバックや見直しを通じて、現場にフィットした形にブラッシュアップしていく姿勢が求められます。
3-3. 企業文化として根づかせる
テクノロジーや制度を整えても、それだけでは十分ではありません。組織の文化として“リモートでも信頼して働ける”という空気を根づかせることが、最終的には働きやすさにつながります。たとえば、心理的安全性を保つために、意見を自由に言えるミーティング文化を醸成したり、Slackでのポジティブな声かけを推奨したりするなど、小さな積み重ねが重要です。
また、成果や努力を称える文化を育てることも、働く側のモチベーション維持に直結します。リモート下では、日常的な“がんばり”が見えづらくなるからこそ、定期的な表彰や感謝を伝える仕組みを取り入れることで、チームの一体感を高めることができます。
文化は制度と違って明文化しづらい分、日々のコミュニケーションや上司のふるまいから育まれます。リーダーが率先してリモート環境での関係構築を大切にすることで、メンバーにもポジティブな行動が波及していくでしょう。

4. Remogu(リモグ)のサポートでリモートワークの課題を解決
リモートワークの課題は、制度やツールだけでは解決できないケースも少なくありません。たとえば、ツールを導入しても現場でうまく使いこなせなかったり、制度があっても働く側が不安を抱えたまま業務に取り組んでいたりすることがあります。
だからこそ、リモートで働くことに特化した外部の支援を受けることで、より安心して取り組める環境が整い、スムーズな業務遂行につながります。
4-1. フリーランスの働き方に最適化された案件紹介
Remoguでは、リモートワークに最適化された案件を多数ご紹介しています。完全在宅、フレックス勤務、週3日からなど、働き方の希望に応じて案件を提案することが可能です。
自分のライフスタイルやキャリアビジョンに合った働き方を無理なく実現できるため、フリーランスとしての安定と自由の両立をサポートします。
フルリモートやリモート中心の正社員求人を専門に扱う転職エージェントです。
フリーランスや副業のエンジニアと企業の業務委託案件を繋ぐリモートワーク専門のエージェントです。
4-2. リモートワークに慣れた企業とのマッチング
Remoguが扱う案件は、リモートでの業務を前提に体制を整えている企業が中心です。たとえば、チャットやオンラインミーティングの頻度、業務報告の方法、納品までの流れなどがあらかじめ明文化されており、コミュニケーション方法や労務管理のルールが明確です。
そのため、フリーランスでもストレスなく業務に集中できるのが特長です。また、初めてリモートワークに挑戦する方でも安心して働けるようなサポート体制が整っています。
4-3. 案件紹介だけでなく、働き方の相談も可能
「リモートでの働き方に不安がある」「長期的なキャリアをどう築くか悩んでいる」といった声に対し、Remoguのコーディネーターが一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。
面談では、スキルや志向に合わせたキャリアプランの整理、希望に合った案件の提案だけでなく、働き方そのものに関するアドバイスも行っています。
エージェントという立場から、働き方の不安や課題にも一緒に向き合い、伴走型でサポートするのがRemoguの特長です。不安を一人で抱えずに、信頼できるパートナーと一緒に次の働き方を見つけてみませんか?
5. まとめ
リモートワークは、働く場所や時間の自由度が高く、これからの時代に合った柔軟な働き方です。しかしその一方で、コミュニケーションの難しさやメンタル面の不安、労務管理の課題など、見逃せないデメリットも存在します。
大切なのは、こうした課題を正しく理解し、企業と働き手がそれぞれの立場で対策を講じていくこと。テクノロジーや制度、そして信頼関係をベースにした企業文化の形成が、リモートワークの成功を左右すると言えるでしょう。
Remoguでは、リモートワークに最適な案件紹介だけでなく、働き方に関する不安や課題にも寄り添うサポートを行っています。「リモートでも安心して働きたい」「より良い環境で自分らしく働きたい」と考える方は、ぜひRemoguのサービスを活用してみてください。